退職金は分離課税の対象です。他の所得と全く分離して、所得を支払う者がその所得の支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで所得税の納税が完結するというものです。
一時所得

退職所得など一時所得(いちじしょとく)は、所得税における課税所得の区分の一つです。
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、一時的なものをいいます)
主な一時所得には、
懸賞や福引き、クイズ番組などの賞金
競馬、競輪、競艇(チャリロトを含む)などの払戻金
生命保険の満期一時金
損害保険の満期返戻金
遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金
但し、宝くじの当選金やノーベル賞の賞金は非課税になります。
一時所得の計算式は
一時所得=総収入金額ー支出金額ー特別控除額(最高50万円)
退職所得控除額の求め方
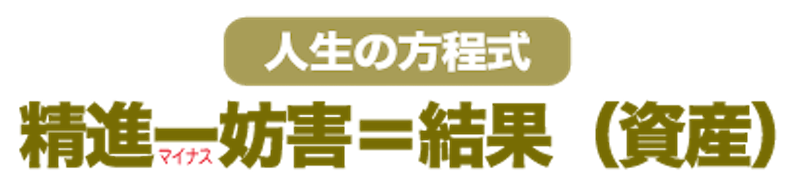
退職手当は一般的に老後の生活のための資金として充てられることが多いので、この退職手当について給与と同様の所得税を課されると大きな負担となってしまいます。
そこで、この退職所得については、その他の所得と分離して特別な計算式でもって税金の計算がされます。
以下の式が、課税される退職所得金額を算出する式です。
1/2の意味は、退職所得は本人にとって重要なお金なのでおまけしてあげましょうという意味だとお考えください。
- 勤続20年以下の場合 40万円×勤続年数(最低80万円)
- 勤続20年超の場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
つまり退職金を得る原価を、20年を超える場合の1年のコストは40万円、20年を超える分の1年のコストは70万円とみなしコストとで計算します。
具体的な計算事例(以下の5ステップで税引後退職所得を確定)

事例 退職手当:30,000,000円(源泉徴収前)、勤続年数:38年の場合
1. 収入金額
収入金額は、源泉徴収前のものとなりますので、この事例では30,000,000円です。
2. 退職所得控除額の算出
上記 課税される退職所得金額を算出する式
勤続20年超の場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年) を適用して計算します。
▼
勤続年数 38年(端数がある場合は切り上げ)
8,000,000+700,000×(38年-20年)=20,600,000円
勤続年数が20年を超えていますので、控除額は18年×70万円に800万円を加えた金額となります。
3.退職所得金額の算出
退職所得金額
(30,000,000-20,600,000)×1/2 =4,700,000円
4. 所得税の算出
上記で算出してきた収入金額から控除額を差し引いたものを半分にしたものが退職所得の金額となります。
ゲンキポリタン大学

「ゲンキポリタン大学」では、「社会人基礎力」をコアにライフシフトをバックアップするさまざまな講座を、さまざまな方を対象に、さまざまな形態で開催しています。ご都合に合わせた形態をお選びください。
無料講座
「社会人基礎力」(全6回)
- 人生100年時代社会人基礎力3つの能力
- 社会人基礎力①|3つの能力と12の能力要素
- 社会人基礎力②|「前に踏み出す力」を育てる3つの能力要素
- 社会人基礎力③|「考え抜く力」を育てる3つの能力要素
- 社会人基礎力④|「チームで働く力」を育む6つの能力要素
- 社会人基礎力に追加された3つの視点
- 12の能力要素①社会人基礎力【主体性】の鍛え方
GTD®勉強会
コラム
-
- 自我と交流分析
- 自他肯定をライフスタイルにする『お粥さんプロジェクト』
- 人生の方程式から外れない<イマジン>3つの自我の使い方
- メンタルモデルを変える5つの心とエゴグラム
- 般若のゴエス|自分を忘れるアサーティブ・コミュニケーション
- 般若のゴエス|アサーション・コミュニケーション|率直について
- ロジカル・シンキング
- ラテラル・シンキング
- システム思考
- 無形資産
- 有形資産(金融資産)
- 自分忘れと自分探し
- 社会人基礎力【主体性】の鍛え方:責任を引き受ける
- 社会人基礎力【主体性】の鍛え方:愛を駆け引きに使わない
- 社会人基礎力【主体性】の鍛え方:自分を愛せる、肯定できるヒト
- 社会人基礎力【主体性】道理・真理に通じていて、なるようになると達観できるヒト
- 社会人基礎力【主体性】過去の評価に左右されないヒト
- 社会人基礎力【主体性】広い視野から人生を見ることができる
関連サイト
ゲンキポリタン大学は(社)いきいきゴエス協会の運営です。

 ご不明な点はコメント欄または友だち追加からお問い合わせください。
ご不明な点はコメント欄または友だち追加からお問い合わせください。
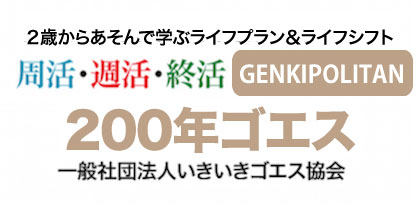


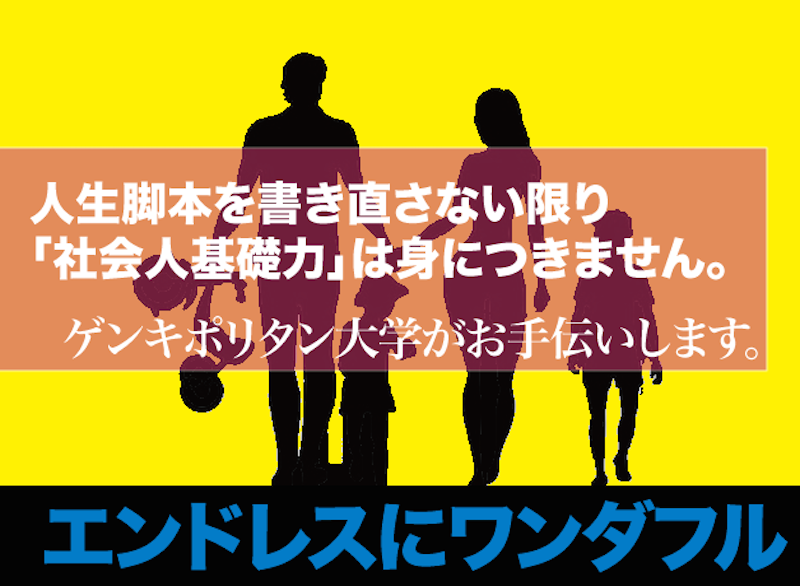
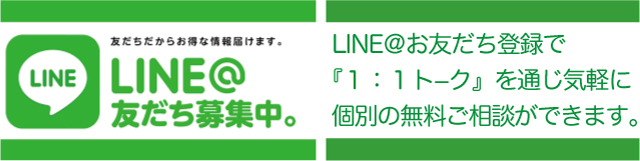
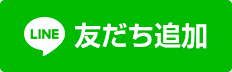

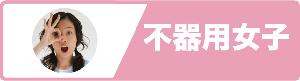




コメント